劇団四季ミュージカル『キャッツ(CATS)』に出てくる、小泥棒「マンゴジェリー」と「ランペルティーザ」。なかなか珍しい発音である上に、どういう意味なのかさっぱり分かりませんよね。
しかし原作『キャッツ ポッサムおじさんの猫とつき合う法』を読んでみると、2匹の名前の由来について書かれていました!
『ジーザス・クライスト=スーパースター』の楽譜をまとめました!
『ジーザス・クライスト=スーパースター』の曲を歌いたい・弾きたいという方は、こちらのブログをご覧ください。
『ジーザス・クライスト=スーパースター』の解説・考察本を執筆しました!
イエス・キリスト最後の7日間とは、どのような日々だったのか?何がイエスを人気にし、なぜイエスは十字架にかかることになったのか?
ミュージカル『ジーザス・クライスト=スーパースター』の奥深さを楽しみたい初心者に向けた、解説・考察本。
Kindle(電子書籍)、ペーパーバック(紙書籍)、いずれも Amazon で販売中。
Kindle Unlimitedを初めてご利用の方は、体験期間中に0円で読書可能!
マンゴジェリー(Mungojerrie)と、ランペルティーザ(Rumpelteazer)の名前の由来は何なのか?
原作には次のように説明がありました。
jerrieはjerryで「便器」、「片手間に仕事をする人」、「肉体労働者」などの意味がある。
teaser(しつこく悩ます人)から由来。つまり、「弱い者いじめする者、他人を悩ませる人」の意味。
―T.S.エリオット『キャッツ ポッサムおじさんの猫とつき合う法
』(p.48)
まずマンゴジェリーですが…えっ?「便器」??
衝撃です。これを読んで一瞬ひるみました(笑)。
「便器」も「片手間に仕事をする人」も「肉体労働者」も全て、このミュージカルに関連がないように思えたからです。
ただ一番しっくりくるのは、2番目の「片手間にちょちょいと仕事を片付けてしまう猫」でしょうね。
泥棒ですからある意味「肉体労働」をしているとも言えますが、さすがに便器は「?」のままです(笑)。
一方のランぺルティーザ(Rumpelteazer)は分かりやすいですね!「何度も何度も人間を悩ませる」猫といった解釈になるでしょう。
片手間で仕事をするのに、人の頭を悩ませる猫…すごいカップルですね!
カタカナに直された日本語で猫の名前を読むだけでは、意味をそこまで深く考えることはないかもしれません。
しかし次の絵本を読むことで、名前にどんな意味があるのかを具体的かつ感覚的に理解できます。原作と併せて是非読んでみてくださいね。
「マンゴジェリーとランペルティーザ – 小泥棒(Mungojerrie and Rumpelteazer)」の、他の記事はこちらから。

それでは皆さん、良い観劇ライフを…
以上、あきかん(@performingart2)でした!
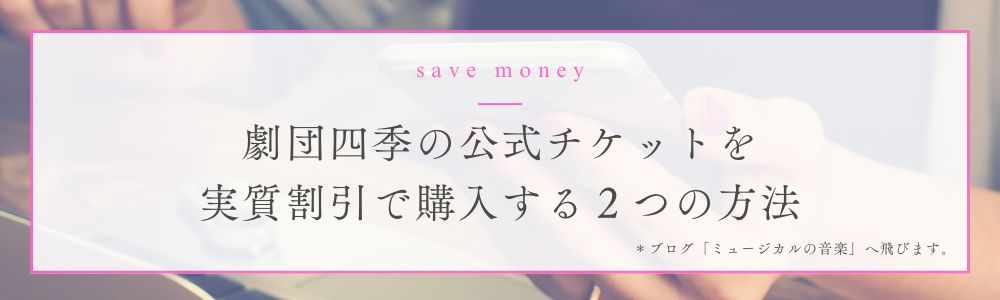




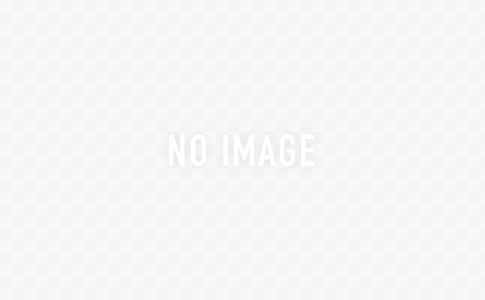





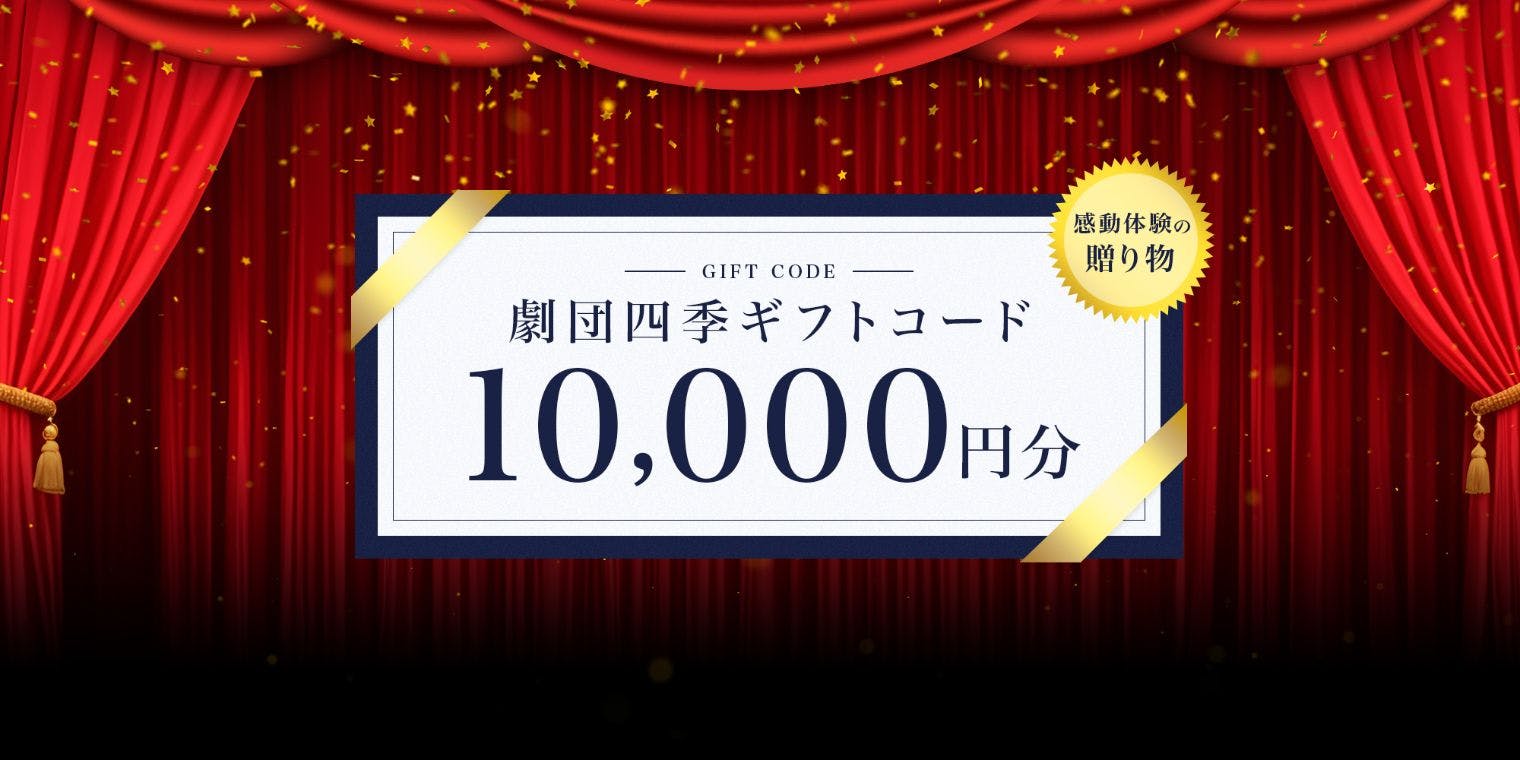




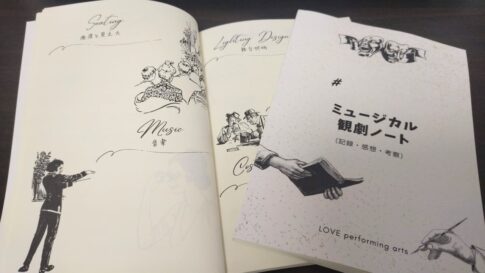



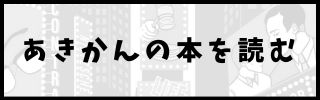
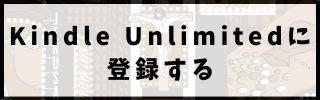
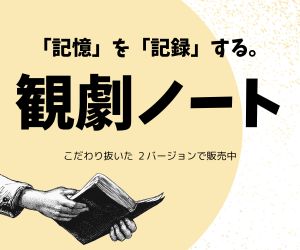

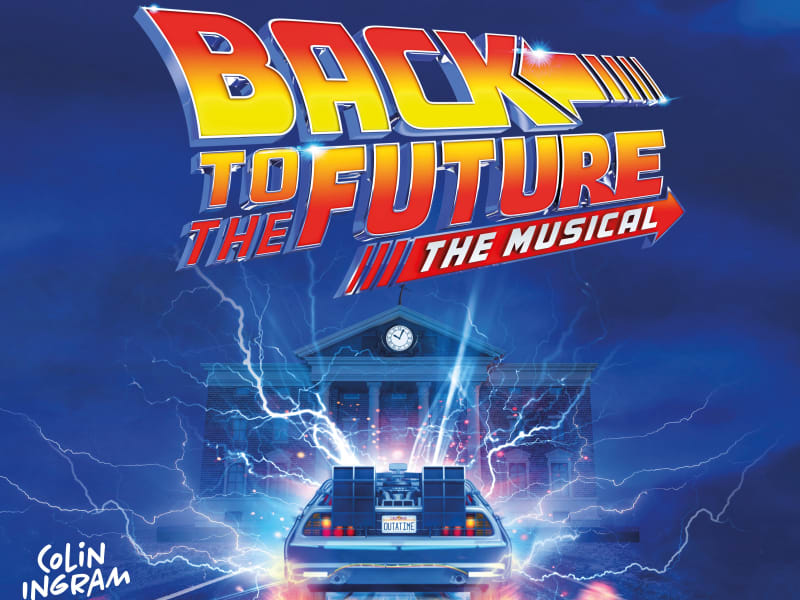
こんにちは!
ミュージカル考察ブロガー、あきかん(@performingart2)です。